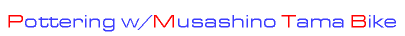多摩川の筏流し
多摩川の筏流しは、江戸時代の中期以降に主として行われ、幕末から明治三十年代にかけて最盛期を迎えたといわれる。奥多摩の山々から切り出したスギ・ヒノキなどの木材を筏に組み、筏乗りが棹さして河口に近い六郷羽田の筏宿まで川下げし、そこからは船積みか、引筏で本所・深川などの材木問屋へと運んだ。

筏流しは、秋の彼岸(九月二十二・三日ごろ)から翌年の八十八夜(五月一・二日ごろ)までと決められていたが、玉川上水の取入口がある羽村の堰を通過できたのは、月のうち五日・六日・十五日・十六日・二十五日・二十六日の六日間に限られていた。
筏乗りは、羽村の堰を過ぎると拝島か立川で泊まり、翌日は府中か調布に、三日目が二子泊まりで、四日目に六郷に着いた。
現在の多摩川原橋の下流、約百メートルの堤防道路脇にある二本の松は、調布に泊まる筏乗りが筏をつないだ松ということで、「筏の松」と呼ばれている。この松はまた別名「舟つなぎの松」ともいう。
筏宿は、「筏の松」から二百メートルぐらい下流の旧鶴川街道の両側にあった。亀屋・玉川屋と呼ばれた二軒で、明治末年から大正期にかけてよく利用されていた。しかし、今はその跡もない。
筏乗りの服装は、印絆天に股引き、ワラジばきで、腰にサイナタ(鞘鉈)を結び付け、晴雨にかかわらず蓑と檜笠を身につけていた。
多摩川の筏流しは、大正の末ごろに急減し、鉄道やトラックなどの陸上輸送の発達とともに姿を消していった。